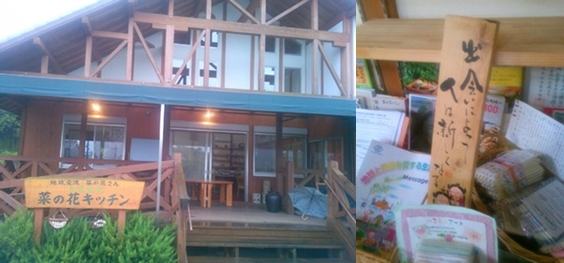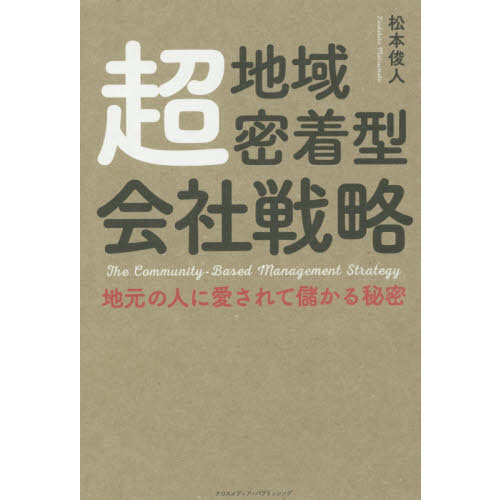日本人にとって『式年遷宮』の意味するものは? 東條英利氏連載コラム no.15
- 2019/06/01 02:55

日本人にとって『式年遷宮』の意味するものは?
東條英利氏連載コラム no.15
今年は神社業界にとって、非常に重要な年と言われています。というのも伊勢神宮と出雲大社という神社界の中でもとりわけ重要視されている両社が共に遷宮を迎えるからです。
伊勢の神宮では、これを『式年遷宮』と呼び、その意味は、読んで字の如く「式年」つまり、「定められた年」に、「遷宮」、「お宮(本殿)を移す」ことになります。こちらは、おおよそ20年つき一度行われることになっておりますが、同様、出雲大社でも、平成の大遷宮と呼ばれる「本殿遷座祭」が行われ、こちらは60年ぶりとなります。そんな両社の遷宮が同じ年に迎えるのは、実は史上初めてのことなのではないかと言われているのです。これは多くの日本人にとって、ある意味、貴重な瞬間に立ち会っていると言える訳です。
では、そんな遷宮は何故行われるのでしょうか。実は、この理由は、はっきりとは分かっておりません。一般的には、遷宮をすることで、そのお宮の建築技法、技術を継承させることにあると言います。確かに、年々、宮大工の数は、その需要の低さから激減しているとも言われておりますので、そういった点では、確かに、必要な存在と言えるでしょう。
ただし、伊勢の神宮に関しては、その理由は諸説ありまして、中には、お宮の鮮度を保持するためにあえて行っているという指摘もあります。これは、神宮の本殿が、柱に礎石を使わず直接柱を埋めていることが、わざと耐用年数を低くするための知恵と考えられており、20年後の式年遷宮に備えるという点においては確かに有効と言えるのかもしれません。
他にも、三元九運と呼ばれる気の流れから算定される暦が、20年に一度という指摘や崇敬者に遷宮という負荷をかけることで、崇敬者の信仰意識を高くつなぎ止めるといった心理学的根拠が上げられることもあります。確かに、最後のものは一見怪しくも見えますが、遷宮に莫大な資金が必要となるのは周知の通りで、とりわけ、伊勢の神宮においては、今回の予算は、総工費550億円以上にも上ると言われております。これは、神宮そのものが、125社から構成されており、その全てが遷座することを思えば、相応の予算が必要となることは分かると思います。神宮の式年遷宮は、10月2日。機会がありましたら、是非、今年は両社に参拝してみて下さい。日本人として大切な何かが分かるかもしれませんよ。
.jpg)